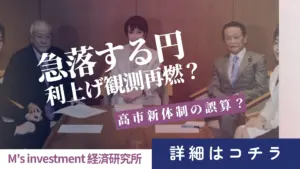日経平均は史上最高でも実感ゼロ?—円安、株高の「ねじれ」を読み解く

株価は絶好調、でも生活は楽にならない。—今の日本では「株高=好景気」という従来の方程式が通用しづらくなっています。本稿では、円安×株高が大企業に先に波及し、中小企業と家計に実感が届きにくい理由をデータで整理。だからこそ必要な自分で守る資産形成まで一気通貫で解説します。
【初心者向け講座】日本国内が貧困に喘ぐ今だからこそ本気で投資を学ぶ為の、無料の投資学習講座!その辺の、情報商材とは訳が違う!
\学校では学べない投資の学びがここにある!/
※AD
なぜ「株高=好景気」に実感がない?
日経平均は2025年も史上最高値圏で推移。一方で家計は輸入物価高の影響を受けやすく、実質的な可処分所得が伸びにくい状態が続いています。背景には、企業の収益構造と経済の二層化があります。
大企業は「海外で稼ぎ、円に戻す」構造
日本の大企業、とくに製造業は海外生産・海外販売の比率が上昇。円安になると、海外で得た利益を円換算したときの金額が膨らみ、業績・株価にプラスが出やすい構造です。
- 製造業の海外売上比率はこの20年で大きく上昇(政府白書)。
- 直近調査では、海外生産比率36%・海外売上比率40%(2023年度)と高水準。
- 輸出価格はドル建て据え置きでも、円安で円建て売上は増えやすい。
結果として、株高・円安=大企業業績の追い風になりやすいのです。
国内の主役は中小企業—しかし円安は逆風に
一方、日本企業の約99.7%は中小企業で、雇用の約70%を担います。内需中心・輸入材を使う企業も多く、円安は仕入コスト上昇=値上げ転嫁の難しさに直結。結果として、利益余力や賃上げ余力が乏しくなります。
- 企業数の99.7%・雇用の約70%を中小企業が占める(政府系資料)。
- 円安による輸入価格上昇は家計のコスト負担も押し上げ、中小の価格転嫁余地を圧迫。
この「輸入コスト増×価格転嫁の難しさ」が、家計・中小企業に好景気の実感が届きにくい核心です。
政策はなぜ「株高・円安」を容認しやすいのか
株高・円安は輸出型・グローバル展開企業の業績に寄与し、株式市場や企業投資のムードを押し上げます。政府・与党が景気下支えを優先すると、結果的に株高・円安を阻害しないスタンスになりやすいのが実情です。
ただし、家計負担や中小企業の生産性課題を踏まえ、中小企業の賃上げ余力や価格転嫁の適正化を狙う政策議論も進んでいます。
だからこそ「自分の資産は自分で形成」
経済の二層化が進むいま、家計は受け身ではなく能動的に資産を築く発想が欠かせません。通貨や収益源を分散し、円安・インフレ・賃金動向に左右されにくいポートフォリオを作りましょう。
- NISAの非課税枠を活かす(長期・積立・分散)。
- 国内外インデックスで通貨と市場の分散。
- 為替ヘッジ有無を使い分けて円安・円高の揺れを平準化。
- 生活防衛費(6〜12か月分)を確保し、積立は自動化。
「企業の構造」に左右されにくい個人のマネープランが、実感なき好景気を“自分ごと化”する最短距離です。
【無料】NISA対応のネット証券で編集部が厳選!
最短即日で口座開設。取引手数料と商品ラインナップで選ぶのがコツ。NISAのつみたて設定で時間分散を。
※AD
投資原資を捻出|家計の固定費を見直しから
電気・通信・保険などの固定費スリム化は、積立額の“恒常的な増額”に直結します。
※AD
【Check Point!】
- 株高・円安は、海外比率の高い大企業の業績に追い風。
- 中小企業(企業数99.7%、雇用約70%)と家計は、円安由来のコスト増で恩恵が届きにくい。
- 政策は景気下支えの観点から株高・円安を阻害しにくい傾向。
- だからこそNISA×分散×自動化で「自分の資産は自分で形成」。
よくある質問|FAQ
円安は本当に日本全体に良いのですか?
輸出大企業には追い風ですが、輸入価格の上昇で家計・中小には逆風も。全体の均衡が重要です。
大企業だけが得をしているのですか?
海外比率が高い企業は恩恵を受けやすい一方、内需・中小は価格転嫁の制約が大きく、差が生じやすい構造です。
個人は何から始めるべき?
まずはNISAの活用、国内外インデックスの分散、生活防衛費の確保、積立の自動化が王道です。